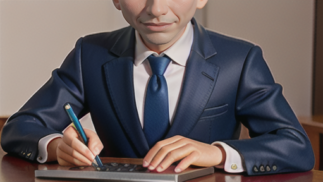投資情報
投資情報 投資の落とし穴!サバイバーシップバイアスとは?
「サバイバーシップバイアス」とは、成功した事例だけを見て、失敗した事例を考慮に入れていない状態を指します。投資の世界では、成功した投資家やファンドのパフォーマンスばかりが目立ちやすく、その裏に隠れた無数の失敗例が見えにくいという状況が発生します。 例えば、大きく値上がりした銘柄や、高いリターンを誇る投資信託はメディアで頻繁に取り上げられます。しかし、投資の世界では成功するケースは少数派であり、実際には同じような投資戦略で失敗した投資家や、基準価額を大きく下げてしまった投資信託も数多く存在します。サバイバーシップバイアスにとらわれると、成功確率を実際よりも高く見積もってしまう可能性があります。冷静な判断をするためには、成功例だけでなく、失敗例からも学ぶ姿勢が重要です。